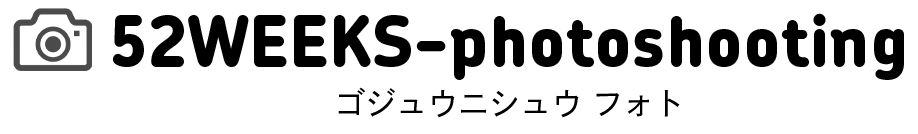2灯目は何を考えてどこに置くべきか
二灯目のいわゆるフィルライトですが、シャドウが明るくなれば何でも良いというわけではなく、自分なりのルールをもって取り組まないと再現性が低くなってしまいます。
暗い部分を「埋める」フィルライト

二灯目は、いわゆるフィルライトと言われますが、直訳すると「埋める」と出てきます。
二灯目の役割としては、一灯目で光を当てることができないシャドウ部分に光を当てる、シャドウ部分を埋めることにあります。
シャドウ部分に光が当たれば良いからといって、どこにストロボを置いても良いかというとそうではなく、しっかり自分の中にルールを持ったうえでライティングしないと、意図したイメージにならず不自然になってしまうと思います。
壁や天井に当たって跳ね返ったことをシミュレートする

では不自然にならないためにどうすればよいのか、セオリーは無いのかという話ですが、私が聞く限りではフィルライトの役割は「壁や天井に当たって跳ね返った光をシミュレート」することだそうです。
つまり、壁や天井があるであろうと考えられる場所、壁や天井があったとしたらこのように光が跳ね返るであろうということをイメージしながらフィルライトを設置すべきということです。
普段自分の身の回りにあるもので自然な雰囲気に見えているものも、実は周囲の壁や天井に跳ね返った光がシャドウ部分を明るくしているために、自然に見えているということです。
窓から入ってきた光で部屋全体が明るく見えるのも、光源の影響だけではなく、壁や天井に跳ね返った影響も大いにあります。
逆に考えると、一方向から来た光が何の障害物も無いところで急に屈折したりしないわけで、一灯しか置いていないのにシャドウが明るいということは、何かしらの物体に光が跳ね返っているということです。
天井バウンスが無難か
最も無難で手軽なフィルライトの入れ方としては、天井バウンスが楽で良いのではと思います。
ただこれは天井や壁に色がついていない無彩色という条件があります。
色がついているとその色を拾ってきてしまい、被写体にもその色が乗ってしまうので注意が必要です。
また、天井バウンス用にストロボを置くときもどこでも良いわけではなく、光源に最も近い真下が最も明るくなることを念頭に置いて、どこにストロボをを置けば自然に見えるかを考える必要があります。
黒レフを置く効果
意図せずシャドウが明るくなることを防ぐために、黒いレフ板を置くこともあります。
撮影環境によっては、壁や天井が近すぎて意図せず光が回ってしまい、コントラストの低い写真になってしまうことがあると思います。こういった場合には壁や天井に黒いレフ板や黒い布を貼り付けるなどして、光が回らないようにすることで、周囲の環境に影響を受けず、ストロボで作った光だけでライティングすることができます。
メインライト(一灯目)がメインに見えるように

フィルライトを入れる上では、メインライトより明るくならないように気をつける必要があります。
あくまで一灯目の光を補うのが二灯目の役割であって、二灯目の方が被写体に与える影響が大きくなってしまうと、それはもう二灯目ではなくメインライトです。
特に注意したいのが、フィルライトを天井バウンスなどにしている場合、一灯目でできたシャドウが強いからといってフィルライトを上げすぎてしまうと、フィルライトが優位になってしまい、しかもそれが天井バウンスのような部屋全体に回る光になっていた場合、かなりコントラストの低い写真になってしまうというものです。
曇りの日を思い浮かべてもらうと分かると思いますが、ああいった方向性の分かりにくい光が最も優位な光になってしまうと、陰影の少ない立体感の出にくい写真に仕上がってしまいます。
もし二灯目でも持ち上げきれない強いシャドウが出ている場合は、もしかすると一灯目の角度が極端につきすぎているようなことが考えられますので、再度一灯目のセッティングを見直すことをおすすめします。
一灯目と色温度を合わせる
二灯以上光源を扱う上で気をつけなければいけないと言われているのが、色温度をすべて同じにするというものです。
ソフトボックスやアンブレラなどを挟む場合や、異なるメーカーのストロボを同時に使う場合などに色温度がバラつきやすくなりますので、突き詰めるのであればどのストロボにどのディフューザーをつけるとどのくらいの色温度になるかを計っておいてカラーフィルターで補正するのが良いとは思います。